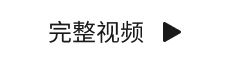-
女性魅力


了解车型 预约试驾
-
生活美学


了解车型 预约试驾
-
运动科技


了解车型 预约试驾
-
活力推荐


了解车型 预约试驾
科技创新
生活美学与前沿科技
了解更多
百公里:(产品: A700)数据来源:第三方检测机构 产品型号:AM1200DT-32;检测依据: T/CAB 0209—2022《电动摩托车用户工况能量消耗率和续驶里程试验方法》;技术要求:在室内环境温度25℃条件下,配置重量75kg,按照T/CAB 0209—2022附录B 基于用户工况的试验循环中B.3综合工况进行车辆行驶,骑行至以下情况时,停止测试:实时车速低于25km/h,且持续10s以上,停止时记录一次充电后的续航里程为126.7km。

生活方式

时尚对话
社群

公益
-
预约试驾
-
门店查询
-
防伪查询
-
骑行指南
科技创新
生活美学与前沿科技
了解更多
-
生活方式

-
时尚对话

-
爱玛社群
爱玛公益

-
预约试驾
-
门店查询
-
防伪查询
-
骑行指南

防伪查询

立即查询
立即查询